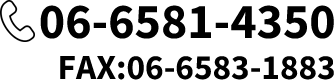A. はいちゃんと規定されています。
JIS H-8641 溶融亜鉛メッキ の 規定
JIS H-9124 溶融亜鉛めっき の 作業手順(施工方法)の規定
JIS H-0401 溶融亜鉛メッキ の 試験方法の規定
A. JIS H-8641 では溶融亜鉛メッキの最低基準が HDZ35(HDZT49) と定められています。この規格を満足する為には350g/㎡(膜厚49ミクロン)メッキを付着させないといけません。ところがM8未満の場合は規定通りに作業をするとピッチが小さい為にねじの谷底にメッキが溜まり ナットが入り難くなってしまいます。遠心分離機等を使って余分な亜鉛を除去すれば、ナットとの勘合はよくなりますが、付着の亜鉛が薄くなり最低基準のクリヤーが出来なくなります。一概には言えませんが、280-320g/㎡ 程の付着と思われます。 したがって、最低基準に満たないメッキ量しか付いていない為、メッキ証明は出せないのです。
但し、半ねじのボルトの場合の様に軸部があると、軸部、頭部に意識的にメッキを厚く乗せる事によって平均値を上げ、結果350g/㎡ (膜厚49ミクロン)を満足させる事も出来ない事はありません。出来ると回答する業者さんはこの方法で処理されますが、意見が分かれるところとなっております。
A. 膜厚計で数カ所のポイントを計測し、その平均値を出すのが本来ですが 350g/㎡ の場合、およそ 50ミクロンです。490g/㎡ の時は70ミクロン。そう g/㎡ の値 を 7 で割った値がミクロンの値となります。 7 は亜鉛の比重なのです。(正確な 亜鉛の比重は 7.133です)
普通一般の電気めっき(ユニクロ、クロメート)などの膜厚は 3-5ミクロン ですからすごく厚く付いていますね。だから ナットはそのままでは入らず、太口のタップ(オーバータップ)したものでないと駄目なのです。
2021年12月20日より改正施行された、JISH8641において、膜厚測定による規格が制定され、HDZT-49(膜厚49ミクロン以上)が、HDZ-35に代わる新規格として使用されることになりました。
A. JIS規格ではそういう規定はありませんが、お客様の希望でそういう指定がある場合、めっき後 数カ所のポイントを計測して 平均膜厚を報告します。しかしながら、 ミクロン値 X 7 という計算式 で g/㎡ の換算値が求められます。 7は亜鉛の比重です。したがって50ミクロンなら350g/㎡の附着量と換算できます。
尚、JISの改正により、膜圧による管理へと改正された、49ミクロンで350g/㎡を満たすと見ています。
(正確な 亜鉛の比重は 7.133である為)
注1:2007年 JIS H 8641の規格改正により 膜厚でも検査ができるようになりました
注2:2021年 JIS H 8641の規格改正により 膜厚での検査に統一されました。
A. どぶメッキ ( 溶融亜鉛メッキ )は膜厚が最低でも約50ミクロンと非常に厚く付着しています。これは電気めっきの約10倍に相当します。その為に使用するナットは通常のタップでは、はめあい が かたくて ボルトなどの雄ねじに入らなくなります。これを解決する為にメッキ前から予めタップをより深く削る事によって スムーズなはめあいとなります。初期にはオーバータップが無かったので、今とは逆に 雄ねじの外径を削って対応していましたが、最近はタップの種類も多くなり、ほぼすべて なっとの様な雌ねじの方で加減するようになっています。
ほんの例外として、どぶのボルトをヘリサート(ワイヤース)に使いたい時などは今でもボルトの山、谷を削ってはめあいを確保することもあります。
経験値ですが、M6 は 0.4ミリ太 。 M8―M10 は 0.6ミリ太。M12 は 0.7ミリ太。M14-M27 は 0.8ミリ太。M30以上 は 1.0ミリ太 程で製作しています。しかし 各サイズ 0.1ミリ程 はメーカーによって異なります。当然大きくなればねじの勘合は甘くなります。 また3種においては、さらに小さくするメーカーもあります。
A. 「ちゃんと オーバータップのナットを使用しているのに 雄ねじに入らない」。机上の計算では起こり得ない事なのですが 雄ねじの打痕傷 や ナットのつまり(溶融亜鉛メッキの際の亜鉛の溜り) などで スムーズにナットが入らない事があります。打痕傷についてはメッキへ出す時にそれの無い事を確認し、取り扱いを丁寧にする事で防止できますが ナットの つまり については 予想が難しく、生地の状態でのタップ面の状況などによって仕上がりが相当変わります。例えばタップを切った際に発生する削り屑などが付着したままで溶融亜鉛メッキを施行すると、その屑の上にメッキが付いてしまい当然固くて入らなくなってしまいます。
充分に前処理をし、その様な事が無い様に指導、注意を払ってはおりますが 電気的に均一に付着させる電気メッキとは異なり 金属(亜鉛)の融けた中に浸漬する 溶融亜鉛メッキの特性から 100%の良品は難しいのが実状です。もとより不良品については皆無にするべく努力いたしますが、メッキの特性上いたしかたない理由が存在する事についてはご理解下さい。
ちなみに、亜鉛の特性上、母材(ボルトやナット)より、亜鉛はやわらかい為、硬くて回らない部分で優しく、硬く詰まっている部分に対し打撃を加えると、亜鉛がネジ山に沿って変形し勘合が良くなる場合があります(無論、すべてのケースで成功するとは限りません)
A. 溶融亜鉛メッキは可能です。しかしながら強力ボルト 六角穴付ボルトに共通する熱処理が表面を硬化させる為に製品によっては上手くめっき加工出来ない事もあります。熱処理の温度や焼戻し時に使用される液体の種類など 詳しくは判りませんが微妙に影響を及ぼします。過去の経験ですが、ねばり 剥離などの不良を生じた事がありました。
現在では弊社の取引きめっき工場では工夫によりほぼ問題を解決してほとんどの強力ボルト 六角穴付ボルトなどの製品の溶融亜鉛メッキは可能となりました。ただし、後述の通り、メッキは可能ですが、ボルトメーカーの推奨は得られておりませんので追加工と同じ取り扱いになる点に、ご留意ください。
A. 強力ボルト 六角穴付ボルトは最終工程で熱処理します。溶融亜鉛めっきは約470℃の液温の中に製品を浸します。この温度が熱処理をした製品にどんな影響を及ぼすのでしょうか?実際に計測した資料などはありません。しかしながら、私共はハイテンションボルトの資料や試験などから判断し、約20%程引っ張り強度が落ちると考えています。ただし、各論が存在しますし、流通レベルでメッキをするとメーカーの保証を受けられなくなります。面倒でもこういった原則をちゃんと説明し、ユーザーの了解を頂いてから作るようにして下さい。
【 追記 】2003年5月から、ドブめっき(溶融亜鉛メッキ)後の強度が 8.8保持出来る 六角ボルト の製品化に成功し、弊社(株式会社 三晃商店 )におきまして、在庫販売を開始しました。これは、焼き入れ焼き戻し時の熱温度とめっき時の熱温度を考慮し、材料区分を選定し、熱処理工場・めっき工場のご協力の下、製品化出来ました。溶融亜鉛メッキ後、定期的にボルトの引っ張り検査を実施し、確認しながら製造しています。
A. ピアス(R)などの、ドリルビスやタップボルトへドブメッキを施すこと自体は、M6以上では技術的に処理は可能ですが、肝心の機能である、直接ねじで対象物に喰いつきねじを立てることができなくなります。理由は、喰いつく為にあるねじ先の刃がドブメッキ処理により切れ味や鋭さを失いなまくらになる為です。(滑って最初のねじが立ちづらくなる)以上の理由により、弊社では、ドブメッキ処理をおすすめしておりません。
鋼の素地の露出した部分の面積が0.01c㎡程度以下であれば亜鉛めっき鉄筋の耐食性に大きい影響はありません。露出面積がかなり大きい場合は、 鋼材表面のさび、油脂、汚れ などを除去し、サンドペーパーなどで研磨してから補修塗装をして下さい。
補修に用いる塗料は厚膜型の高濃度亜鉛末塗料が適当で、特に有機系の厚膜型高濃度亜鉛末塗料が付着性の点ですぐれています。なお、塗膜の乾燥時間は常温で16時間程度を見込んでおくとよいでしょう。
A. 亜鉛は必須元素です。
生体は、それが必要とする元素を大気や水、土壌などの自然環境から直接または食物を介して間接的に取り入れています。生体細胞がこれら必須元素を必要量摂取できていれば生育は順調に進みますが、摂取量が少なすぎると生育不良を起こしたり、あるいは過剰に摂取すると有害となる可能性があります。
1.亜鉛欠乏による障害
生体に亜鉛が欠乏した場合の障害に関しては 、主なものとしては (1)味覚・嗅覚障害 (2)成長の阻害 (3)生殖機能の障害 (4)うつ状態と食欲不振 (5)易感染症の増大 などがあります。
アメリカのN.R.C.の発表によると、食物から摂取する亜鉛の推奨飲食規定許容量として
子供(1~10歳) 10mg/日
男性(11~51歳以上) 15mg/日
女性(11~51歳以上) 12mg/日 とされています。
2.亜鉛による中毒
生体に有効ないかなる栄養素、薬物といえども、それが過剰に摂取されれば有害となります。亜鉛においても同様な事が言えますが、亜鉛の毒性は極めて低く、平常の摂取量と、何らかの有害な作用を示すような摂取量との間には広い幅があります。
人体への影響については、経口中毒と吸入中毒に分けることができます。
(1)経口中毒
亜鉛の塩類は消化器等の粘膜を刺激して、大量摂取すると致命的な虚脱を招くことがあります。経口致死量は、硫酸亜鉛として摂取した場合、5~15gとされています。
(2)吸入中毒
産業現場では、金属亜鉛の溶融、黄銅または青銅の鋳造・加工・ろう付け、亜鉛めっき鋼材の溶断・溶接などの作業に際して発生する酸化亜鉛のヒュームの吸入によって発熱症状を招くことがあります。これを亜鉛熱、真鍮熱、金属熱などと呼んでいます。主な症状は、吸入後2~8時間頃に現れる発熱症状で、インフルエンザの様な悪寒を伴い、数時間を経過すればほとんどが完全に回復します。